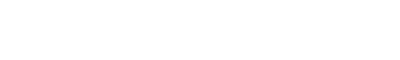胃がん
- HOME
- 胃の疾患:胃がん
胃の上皮細胞ががん化することで発生するがんが胃がんです。胃に発生する悪性腫瘍はいくつかあります。
胃がん以外では悪性リンパ腫やGISTなどを代表とする消化管間葉系腫瘍があります。一般的な胃がんは胃の悪性腫瘍の内、胃の上皮組織から発生する”腺がん”というがんです。
また特殊なタイプの胃がんとして、胃壁に沿って染み込んでいくように広がり、胃壁が硬くなっていく”スキルス胃がん”と呼ばれるタイプの胃がんもあります。胃の壁の組織的な構造は何層もの層構造になっており、早期の胃がんは一番表層の粘膜のみに病変が存在します。その後がんの進展とともにどんどん深くがん組織が浸潤し、リンパ管や血管を巻き込み全身に転移していきます。
胃がんの症状
早期の胃がんは基本的に症状を呈することはありません。胃がんが進行し、腫瘍のサイズが大きくなることで色々な症状を呈することになります。下記は胃がんの症状として有名な兆候です。
食欲不振、体重減少
胃がんが進行することで体重が減少することがあります。これは胃がんによる必要エネルギーが増加することよりも、必要な栄養(カロリー)が摂取できなくなることに起因します。腹痛や吐き気、早期に満腹感を感じることで、食事の摂取量が低下し、体重が減少していきます。
早期満腹感、胸焼け、吐気、胃部不快感
胃がんが増大することで、胃の拡張性が悪くなり、また胃の容量が少なくなることで食事をしても早期に満腹感を自覚することがあります。胃の入り口(噴門部)の機能が低下し、胃酸を逆流しやすくなる場合もあり、胸焼け症状の原因にもなります。また胃の蠕動運動が低下し、胃の内容物の進みが悪くなることで吐気をきたすこともあります。これらの症状は胃がんのサイズが増大することで生じる症状です。
腹痛(心窩部痛)
鳩尾(みぞおち)の痛みを呈することがあります。疲労感や一時的な軽い痛みのこともありますが、痛みの程度が重くなり、持続するようになると胃がんの進行の影響の可能性があります。
嚥下困難
胃がんが増大することで、胃の拡張性が悪くなり、また胃の容量が少なくなることで食事をしても早期に満腹感を自覚することがあります。また胃がんが胃の入り口付近(噴門部)にできると、食道で食べ物がつっかえてしまし、食べ物を飲み込んでも胃の中まで食べ物が進まない状況になります。そのことで嚥下困難の症状をきたし、誤嚥の原因になります。
貧血、黒色便、吐血
粘膜を欠く潰瘍を形成するタイプで生じる症状です。胃潰瘍と同じ所見を呈して、潰瘍底に露出する血管(動脈や静脈)から出血をきたします。出血量が多い場合は血を吐くこともあります。また少量の出血が持続的に継続する場合は黒色の便が出ることがあります。出血の結果として貧血を呈して、息切れや動悸などの症状が出現することもあります。
上記の症状があるから必ず胃がんがあるわけではありません。これらの症状を呈する疾患は多くあります。鑑別のためにも、これらの症状がある場合は胃内視鏡での精査が必要です。
胃がんの原因
胃がんには明確なリスク因子が存在します。ヘリコバクター・ピロリ菌の感染です。世界保健機関(WHO)も1994にピロリ菌を明確な胃がんの危険因子として定義しております。これは喫煙(タバコ)と肺がんの関係と同じレベルの関係性です。その他の要因も報告されています。
ヘリコバクター・ピロリ菌
胃がんの最も明確なリスク因子です。胃粘膜にピロリ菌が感染することで、慢性胃炎を引き起こします。これは萎縮性胃炎と呼ばれる状態で、一部の粘膜は腸上皮化生と呼ばれる変化を起こします。これらの粘膜変化が胃がんの前がん状態と言われております。
日本からの研究ではピロリ菌が感染している胃からは10年で5%が胃がんに進展することが報告されています。100,000人のピロリ菌保菌者がいれば10年で5,000人に胃がんが見つかることになります。また別の研究では、ピロリ菌に感染している人では,生まれてから85歳までに胃がんに罹る確率が男性で17.0%(約6人に1人),女性で7.7%(約13人に1人)に上る可能性が高いことが報告されました。 ピロリ菌の除菌治療後に関しては、国立がん研究センターの報告では胃がんの既往がない方がピロリ菌の除菌治療をした場合、将来の胃がんリスクは約3分の1になると言われています。また胃がんの治療をした方でもピロリ菌の除菌治療後は胃がんの再発率は半分になると言われております。
いずれにしてもピロリ菌がいる人、または除菌治療した人は積極的に胃内視鏡で精査、または経過観察が必要です。
塩分、塩分添加食品
日本は食文化として塩分の摂取が多く、ソルトアイランド(塩の島)と呼ばれています。そして塩分の摂取は胃がんのリスクの危険因子であるとされています。食塩の過剰摂取は胃の粘膜を損傷し、発がん感受性を上げるとされています。この作用は食品由来の発癌物質の作用を促進するように働く可能性が指摘されています。現在の胃がんの患者数の減少は、冷蔵技術の発達とともに塩分を使用した食料保存(塩漬けなど)が減ったことが一因として関連していると考えられております。
その他のリスク因子
肥満は胃がんのリスク因子と考えられておりますが、海外での報告ではBMI>25以上が肥満と定義されており、日本人に当てはまるかははっきりしません。そのほか喫煙や加工肉の摂取も胃がんとの関連が強いとされております。
胃がんの治療法
胃がんの治療は主に内視鏡的切除術、外科的切除術、化学療法(抗がん剤)や放射線治療があります。特に日本では内視鏡技術が世界的にもトップクラスの国であるため、胃がんの内視鏡的切除術の治療成績が高いとされています。
1. 内視鏡治療
早期がんに対して胃カメラでがん細胞を除去します。日本では内視鏡的粘膜下層剥離術ESD (Endoscopic Submucosal Dissection)の技術が世界でも先進的とされ、広く行われております。
2. 手術
病状に応じて胃の一部または全体を切除します。場合によっては周辺臓器も摘出します。
3. 化学療法
手術が難しい場合や術後再発を予防するために使用されます。