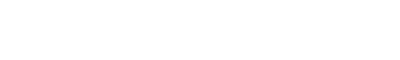2025.04.04
下血が出たらどうする?原因・病気・検査方法を徹底解説
下血とは?血便との違いを知ろう
下血の定義とは?
「下血」とは、消化管(食道、胃、小腸、大腸)のどこかから出血し肛門から排泄されることを言います。医学的には食道、胃、十二指腸など上部消化管からの出血が「黒っぽい便」として排出されることを指します。一方、血便とは大腸や肛門など下部消化管からの出血が排泄されることを言います。医学的には区別されて使われますが、一般的にはほぼ同じ意味で使用されております。
血便との違いを比較(色・出血部位の違い)
下血とまとめて言っても、出血する箇所の違いで色調や性状に変化があります。
例えば、胃や小腸、肛門から離れた小腸から出血する場合では黒色や暗赤色に色調が変わります。血液は酸化すると黒く変色するため、胃に近い場所の出血では、胃酸に血液が触れることで酸化し血液が黒くなります。胃酸によって酸化した黒色便はまるで石炭のような黒さに見えることからタール便とも呼ばれることもあります。また空気に接触しても酸化するため、腸管の中に長時間留まっていると赤黒い便となることもあります。出血がなくても、お飲みになっている薬(代表的なものだと鉄分のサプリメント/薬剤など)でも黒色の便が出ることがあります。黒色の便が出た場合、頻度の多いものとしては胃/十二指腸潰瘍があり、危険なものとしては胃癌などからの出血もあるため胃カメラ検査が推奨されます。
医学的に「血便」と呼ばれる真っ赤な鮮血が出た場合、出血から時間が経っていないことが予想され、肛門に近い消化管(大腸や肛門)からの出血が想定されます。肛門の近くであれば痔出血や裂肛、大腸からの出血であれば憩室出血や虚血性腸炎や感染性腸炎、腫瘍による出血などが原因として疑われます。この場合は大腸や肛門を観察するのに適している大腸カメラでの検査が推奨されます。
下血の原因|考えられる病気一覧
痔や裂肛による下血
最も頻度の多い下血として痔(肛門周囲の静脈のうっ滞)や裂肛(肛門の皮膚が裂けること)があります。これらは肛門に極めて近い場所や肛門自体から出血するため、典型的には肛門周囲の疼痛や、鮮やかな色の出血を伴うことが多いといわれています。何度も繰り返し出血し、生活へ影響を与える場合は外科的な治療の対象となりますが、基本的には排便のコントロールを行うことで経過観察可能です。
大腸ポリープ・大腸がんの可能性
「大腸ポリープ」とは大腸の表面にできる隆起病変(腫瘍)の総称のことです。大腸の良性腫瘍(過形成ポリープ、大腸腺腫Adenomaなど)や大腸癌もまとめてポリープといいます。ポリープは良性や悪性に関わらず、サイズが大きくなってくると、擦れによる表面からの出血を起こすため、持続的な下血(血便)を起こす可能性があります。
胃潰瘍・十二指腸潰瘍による下血
胃や十二指腸に潰瘍(消化管の表面粘膜の欠損を伴う傷)からも出血をきたすことがあります。前述したように胃の近くから出血した場合の下血は、痔や裂肛から出血するような鮮やかな血液ではなく、黒色もしくは暗赤色となることが多いため色調が出血した消化管の箇所を推測する手掛かりとなります。
感染症や腸炎による出血
ウィルスや細菌による感染性腸炎や腸の血の巡りが悪くなることで起きる虚血性腸炎など腸炎でも下血を起こす場合があります。感染性腸炎などで下血する場合、腹痛や嘔吐、下痢を同時に起こすことが多く、病歴から診断することができます。虚血性腸炎も先行する腹痛があり下血であり、多くは病歴から診断されます。また頻度としては低いですが、慢性的な腹痛や下血をきたす場合、自身の免疫が過剰に働き自身を攻撃する腸炎(自己免疫性疾患)として潰瘍性大腸炎やクローン病があります。
下血が出たときの受診の目安
放置してはいけない危険な下血
大量に下血した場合は、皆さんすぐに病院を受診される方が多いと思いますが、実は危険な下血は少量ずつ持続的に起こることもあります。大腸癌による慢性的な少量の血液付着を伴う下血もあれば、自己免疫性腸炎(潰瘍性大腸炎やクローン病)による長期的な下痢や腹痛を伴う下血もあります。持続的(2-3週間など)に下血が少量持続する場合は危険なサインかもしれません。また胃/十二指腸潰瘍や胃癌などの胃に近い出血は、便が黒っぽくみえる(黒色便)下血となり、こちらに関しても出血している原因をはっきりさせず放置すると、貧血や癌が進行する可能性があります。このように下血があった場合は大腸カメラだけでなく、胃カメラも併せて行うことが推奨されます。
様子を見てもよい下血とは?
基本的に血が出ている下血や血便で安心できるものはありませんので、内視鏡の専門医を受診することが強く推奨されます。特に下血で特にふらつきなど貧血による症状がある場合は緊急で胃カメラや大腸カメラでの精査が必要です。最近1~2年の間に大腸カメラの経験があり、硬い通常の色調の便などの横に鮮血の血液が分かれて付着している場合などは数日様子を見ていただくことも可能です。その場合は肛門からの一時的な出血であることが考えられますが、最近で大腸カメラを受けられたことのない方で、持続する場合は一度大腸カメラをお勧めします。
下血の検査方法と治療法
大腸カメラ検査の重要性
以上のように下血を起こす病気は様々であり、下血の色調などである程度推測はできますが、診断には直接の大腸カメラでの確認が必要です。CT検査などの画像検査でも大きな隆起した病変などは見つかりますが、小さな病変や粘膜のわずかな炎症などは見つけることはできず、またポリープがあった場合も大腸カメラでのみ切除などの治療を行うことができます。大腸の病変を診断/治療する上では、大腸カメラは必須かつ、代わりのきかない検査であり非常に重要です。またポリープが下血の原因ではなくとも、過去検査歴のない方では大腸カメラで小さなポリープも見つかることがあります。良性のポリープであっても癌化する可能性のあるポリープもあるため切除することで、将来の大腸がんリスクを減らすことができます。
胃カメラ検査で判明する病気
下血が黒色便である場合は、胃やその近くの消化管からの出血が疑われるため、まず胃カメラ検査を先行して行います。胃カメラで確認できる範囲は、咽頭・食道・胃・十二指腸の途中までになります。その範囲にある病気は診断可能で、出血する危険な病気では代表的なもので食道癌・食道静脈瘤・胃癌・胃潰瘍・十二指腸潰瘍などがあります。いずれの病気も放置すると、病気の進行や大量出血を起こす可能性があり、非常に危険ですので放置せずに病院を受診されてください。
治療方法(薬・内視鏡治療・手術)
治療についてはまず胃カメラと大腸カメラで治療の必要な病気があるか診断することが必要です。その上で病気にあった治療法が決定されます。胃潰瘍・十二指腸潰瘍などでは出血している箇所があれば内視鏡での止血処置が必要になります。また胃酸による刺激が胃潰瘍や十二指腸潰瘍の原因または悪化させる要因でもありますので胃酸分泌抑制剤を使用しお薬での治療を行います。裂肛や痔出血の場合、基本的には便秘や排便時の力のいれ過ぎなどが原因であることが多く、排便習慣の改善や下剤の使用による便性状の改善を行い、原因の治療を行います。大腸ポリープがあった場合は、大きさや見た目で治療方針を決定します。20mmまでの小さなポリープで良性が疑われるものや表在癌(粘膜の下に浸潤していないもの)についてはスネアという金属の輪っかでポリープ切除(ポリペクトミー)を行います。また残念ながら内視鏡での治療適応外となってしまったような進行癌については、CT検査などで評価を行い、手術の適応があれば外科的に手術を行います。このように下血といっても様々な原因とそれぞれに適した治療法があり、まずは確実な診断を行うことが大切です。
下血を予防する生活習慣
消化器を健康に保つ食生活
消化管は食事が通過する経路であり、食生活が病気に関わることがあります。アルコールを摂取しすぎると肝硬変という肝臓の線維化を引き起こし、悪化すると食道静脈瘤破裂という異常血管からの大出血を引き起こします。またアルコールそのものが胃潰瘍・十二指腸潰瘍の原因であり、状況を悪化させる可能性があります。
便秘が慢性的になり、排便時にいきんだりすることが多くなると裂肛や痔核出血を引き起こします。そのような病気の予防ももちろん大事ですが、便秘は様々な病気と関連があることが最近の研究で判明してきました。慢性の便秘は大腸癌や血管の病気、腎臓の病気などのリスクになることが明らかになっており、消化管のみの問題ではありません。普段から不溶性食物繊維を含む食材(海藻類やきのこ類、野菜やくだものなど)をバランスよくとるように気を使う食生活を心がけられてください。
また大腸ポリープが発生するリスク因子として、食生活の関わりも指摘されています。欧米のような脂身や揚げ物など高脂質で野菜などをとらない低繊維質の食習慣は大腸ポリープのリスクになります。便秘や肥満、飲酒習慣の改善が様々な病気の予防に繋がっているため、食生活を見直すことは非常に重要となります。
ストレス管理と腸内環境の改善
ストレスも排便の習慣に関与することが言われています。ストレスがかかった状態では自律神経の中の交感神経が活発になり、消化管の動きが悪くなるため便秘を悪化させてしまいます。適切な運動習慣がストレスと排便習慣の改善には有効であり、運動習慣がない便秘症の方などは散歩などから始めることをお勧めします。腸内環境は便秘と強い関連があります。腸内環境とは腸内の細菌叢のことで、腸内には様々細菌が繁殖していますがそのバランスが重要です。腸内環境を改善させることで、便秘の解消につながるため、食生活(特に野菜、果物、ヨーグルトなどバランスよくとること)や運動習慣を改善させ腸内環境の改善を目指しましょう。
まとめ|下血が出たら早めの受診を!
下血については様々な原因があり、それぞれに適した治療方法があります。まずは診断を行うことが重要であり、そのためには専門性の高い診察や血液検査、胃カメラ、大腸カメラなどの検査が必要です。胃カメラや大腸カメラは敷居が高く、怖い検査だと思われがちですが、鎮痛剤や鎮静剤(痛みをとったり、眠くなるお薬)を使用することで苦痛なく検査が可能です。下血した場合は、ご自身で悩まず、まずは専門医に受診しご相談ください。